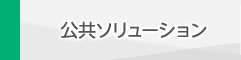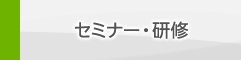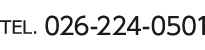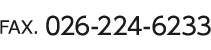ソーシャルディスタンスで再評価される地方の価値<2020・06・11>
体に感じる地震が増えているが首都圏は大丈夫か
4月頃から体に感じる地震が多くなっている。気象庁のホームページを見ると、4月以降に「ほとんどの人が恐怖を感じる」とされる震度4以上の地震は18回起こっている。うち震源地が長野県というのも3回あるが、千葉県、茨城県が6回と多い。「首都圏直下型地震の予兆なのか」と不安が頭をよぎる。
首都圏直下型地震については、マグニチュード7級の地震が今後30年以内に70%の確率で起こるとされている。予測される最悪の人的被害は、「冬の夕方で風速8m/sの風が吹いている」という条件が揃った際に23,000人の死者が出るというものだ。これは東日本大震災の15,894人、阪神淡路大震災の6,434人をはるかに上回るもので、人口密集地ゆえの甚大な被害と言える。さらに人口密集地ならではの「帰宅難民」というものも数が尋常ではない。東京都だけで最大490万人、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県を併せた1都4県では最大800万人になる。
人口が密集することはサービス業を盛んにしたり、企業のイノベーションを加速させるなど経済的なプラス面は大きい。しかし、地震などの自然災害が及ぼすマイナス面を考えるなら、こうしたプラス面も色褪せる。首都圏直下型地震の死者23,000人という被害が推計された報告書(注1)は2013年に発表されたものだが、東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)への人の転入はその後も高い水準で続いている。昨年(2019年)の数値(転入者が転出者を上回る「転入超過」の数)を確認すると、14万8,783人と長野県上田市に匹敵する人数が東京圏に流れ込んでいる。
新型コロナウイルスが突いた人口密集地「東京」
今回の新型コロナウイルスの感染拡大も、人口密集がもたらしたマイナス面だ。東京都では、最大の感染者を出しており、大阪府、神奈川県と続く。人口が多いから、割合で考えても感染者が多いのは当然とも言えるが、人口密度との関係で見ると、わずかだが更に高い相関が見られる。人と人との接触で感染するウイルスゆえに、人口密度が高いほど感染リスクも高くなる。例えば、感染者ゼロを維持している岩手県(2020年6月6日時点)では1 k㎡あたり83人という人口密度であるのに対し、東京都では6,168人と二桁も高い。更に区部では15,428人であり、豊島区、中野区、荒川区、文京区、台東区などは2万人を超す。
ただ、全国で最も人口密度が低いのは北海道で、1 k㎡あたり68人となっている。ところが公表されているように、現状感染者数は全国4位の高さだ。2月に開催された「さっぽろ雪まつり」を訪れた外国人観光客が北海道各地から集まった人と接触したことで、感染が拡大したことが主な理由とされている。
過疎地域でもイベントで人が密集し、その中に感染者が居れば容易に感染拡大は起こりうることが分かる。しかし、だからと言って東京都の人口密度が高いことが問題なしということにはならない。感染予防のためのソーシャルディスタンスである2mという距離は、東京圏の満員電車で維持することは難しい。通行人の肩が触れ合うほどの渋谷や新宿などの駅前では、どうやって歩けばいいのか。
存在自体がソーシャルディスタンスな長野県
さて、そこで長野県である。長野県の人口密度は1 k㎡あたり154人であり、全国で38位の低密度県だ。ほとんどの町や村は、その存在自体がソーシャルディスタンスだ。
そして地震も少ないと言いたいところだが、それ相応にはある。気象庁の「2019 年の地震活動について」を見ると、年間90回発生しており、全国で13番目だ。長野県には糸魚川静岡構造線と言う巨大断層が県土を貫くように走っている。近年では2014年11月に糸魚川静岡構造線の北部に位置する神城断層で地震が起き、白馬村を中心に甚大な被害が出た。家屋の全壊は81棟と、長野県では過去に類を見ない規模となった。
しかし、これでも被害は桁違いに少ない。神城断層地震はマグニチュード6.7だから、先に見た首都圏直下型地震が想定する規模と同程度だ。首都圏直下型では、揺れによる全壊家屋が約175,000棟と被害の桁が4つ跳ね上がる。さらに神城断層地震では40余名の負傷者は出たものの、死亡者はゼロという奇跡的な人的被害ですんだ。首都圏直下型であるなら、建物倒壊による死者は最大約11,000人に上る。
この違いは、白馬村に残る昔ながらのコミュニティが、迅速な安否確認と救出を可能にしたと説明されている。しかし、より根本的には人口密度の圧倒的な違いであろう。当然の話だが、自然災害が起こると人口密度が高いほど被害に遭う人の数は多くなる。極端な話、どのような大地震が起きようとも誰もいない場所であるなら、それは災害とは呼ばない。
快適な生活環境 ≒ ソーシャルディスタンス
地震やコロナ禍に見るように、人口密度は自然災害の被害規模と大いに関係がある。だから、安全のためには適当な人口密度や人と人との距離が必要となる。その一つが先にも書いたソーシャルディスタンスというものだ。この言葉は、公衆衛生を語る際に「疾病の感染拡大を防ぐため意図的に人と人との物理的距離を保つこと」を意味する専門用語だ。およそ2mの距離を保つことで、他人からの感染が防止できるとされている。
本来人は、感染防止とは別に他人との一定の距離を保とうと無意識のうちに行動している。これは「パーソナルスペース」という言葉で呼ばれている。このパーソナルスペースについて、エドワード・ホールというアメリカの文化人類学者は4つに区分している。生活の場面に応じ、自分も相手も不快に感じない最適な距離を研究したものだ。極めて親しい人とは手をつなげるぐらいの距離である「密接距離」(40cm程度) (注2)、家族や親しい友人などとの距離は会話ができる程度の「個体距離」(45cm~120cm)、一般的な他人と関わる時や公的な場所での距離は「社会距離」(120cm~365cm)、講演会などで講演者と聴衆との距離などは「公衆距離」(365cm以上)としている。これを見ても、一般的に関わる他人との関係では、120cm~365cmの距離を取ることが自然で快適であることがわかる。
こう考えるなら我々が社会生活を営む上で快適な人と人との距離は、ソーシャルスペースが示す「社会距離」程度であり、それは奇しくもソーシャルディスタンスが求める距離でもある。
首都圏と異なり地方では、普通の暮らしの中でソーシャルディスタンスが確保できる。人口密度が低いゆえに、自然とそうした構造が出来上がっているのだ。
備えあれば患いなし
いずれにしても、首都直下型地震のリスクは高まっており、新型コロナウイルスも第2波の到来が警告されている。であるなら、そうした危機に対しいくつかのシミュレーションを考え、事態に備えることで、想定内の環境変化として危機に対応することが出来る。そうした対応策の一つとして、「地方の選択・活用」というものも大きな比重を占めていくのではないか。
自然災害のリスクが高まっている今日、お荷物とさえ見なされていた過疎地を抱える地方の価値が見直されていくように思う。
(注1)「首都圏直下型地震の被害想定と対策について」(平成25年12月)中央防災会議 首都圏直下型地震対策検討ワーキンググループ
(注2)エドワード・ホールの4区分について、原文はインチ、フィートで記述されているため、それぞれの距離はおよそのセンチ換算で表示
(資料)エドワード・ホール「かくれた次元」みすず書房
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233