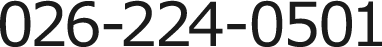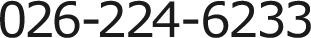注目され始めたエシカル消費<2019・09・09>
エシカル消費とは
「エシカル(ethical)」は、倫理的、道徳的という意味の形容詞です。つまり、「エシカル消費」とは、「人や社会、地球環境、地域に配慮して作られたモノを購入・消費すること」と定義され、近年注目されています。
エシカル消費が注目され始めた背景には、貧困や人権、気候変動などをどうすれば解決できるかという世界的な課題があります。課題解決に向けた1つの対応が、人や社会、地球環境に配慮した消費です。これは、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の17の目標の1つである「持続可能な生産消費形態の確保」に関連する取り組みでもあります。
我が国では、消費者庁が2015年5月から2年をかけて「『倫理的消費』調査研究会」を開催し、エシカル消費の普及・啓発に向けて主体となる消費者や事業者、行政が取り組む上での必要性や意義などをまとめています。さらに長野県でも今年1月に長野県版エシカル消費「人・健康・地域・社会・環境に配慮した思いやりのある消費」の推進に取り組み始めています。
エシカル消費には、リサイクルや地産地消、障がい者の支援につながる商品の購入などさまざまな形があります。具体的には、使い捨てのものではなく長く使えるものを選ぶ、リユース・リサイクル製品を選ぶ、地域にある資源を優先して消費する、被災地を応援する消費をする、障がい者の就労を支援する製品を選ぶ、などが挙げられます。人や環境、地域などに配慮した日々の消費行動を通じて、世界や地域が抱える課題解決の一端を担うことができる、それがエシカル消費です。
まだ低いエシカル消費の認知度
県内でのエシカル消費の認知度はどうでしょうか。当研究所が今年7月に県内の消費者に行った消費動向調査の中でエシカル消費に対する認知度を尋ねたところ、「聞いたことがあり、意味も知っている」は6.5%に過ぎず、「聞いたことがあるが、意味は知らない」(14.8%)を併せても2割程度にとどまりました。一方、エシカル消費につながる取り組みを行う企業や、製品・商品に対するイメージについては、「好感が持てる」が19.7%、「どちらかというと好感が持てる」が32.3%と半数以上が好感を持っています。
さらに、エシカル消費への今後の取り組み意向を尋ねると、「積極的に取り組みたい」が8.4%、「どちらかというと取り組みたい」が31.4%と、約4割が前向きな回答を示した一方、「わからない」(44.6%)、「(どちらかというと)関心がない」(5.9%)、「関心がない」(9.7%)と、6割が消極的な回答をしています。こうした層にエシカル消費をどう意識付けしていくかが、取り組みを広げていく上での課題です。
エシカル消費を推進する県やエシカル消費につながる取り組みを行う企業が、その必要性や意義などを積極的に情報発信し、消費者の取り組みを促していくことが重要と言えるでしょう。そして消費者には、誰が、どこで、どのように作った製品か、などを意識しながら買い物をすることが、世界的な課題や地域の課題解決につながるんだということを自覚することが求められるのではないでしょうか。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233