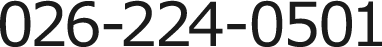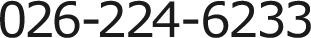注目される3Dプリンター住宅の実用化<2025.4.11>
3Dプリンター住宅とは
3Dプリンター住宅とは、建築用3Dプリンターを活用してコンクリートやモルタルなどの素材を一層ずつ積み重ねて出力(構築、印刷)し、建築する住宅です。
国内では、(株)大林組(東京都)が3Dプリンターによる建築物として国内で初めて建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を取得した建屋を建築したほか、セレンディクス(株)(兵庫県)が商用建築物として日本で初めて建築・販売を行っています。このほか、清水建設(株)(東京都)や(株)竹中工務店(大阪府)、(株)Lib work(熊本県)など、複数の企業が3Dプリンターによる建築物の開発を進めています。
3Dプリンター住宅の特徴と課題
セレンディクス(株)が、24年10月に石川県珠洲市において建築・販売した「serendix50」(写真)は、間取りが1LDKの平屋建てで延床面積が約50㎡、キッチン、バス、トイレといった水回り設備を完備した、鉄筋コンクリート造となっています。
serendix50は、事前準備として、建築に用いる壁や基礎などの部材を3Dプリンターで出力します。その後、基礎工事、躯体工事、外装内装工事を経て、完成、引き渡しとなります(図表)。木材建築や従来のRC建築の工法と大きく異なるのが、(1)事前準備で出力した部材を用い、(2)基礎工事、(3)躯体工事(組み立て)を行う点です。
躯体工事にかかる時間はわずか44時間30分で、工場での部材の出力から完成まで、およそ1カ月程度で終了するなど、短工期であることが大きな特徴です。この特筆すべき建築スピードは、一般住宅のみならず、災害時の仮設住宅の建築など、緊急時の住居不足の解消に有用と思われます。
このほか、3Dプリンターによる部材の出力では、自動的に材料を積み重ねるため、手作業が少なく省人化につながっています。さらに、設計図通りに無駄なく、効率よく材料を使用できるため、資材の廃棄ロスが少なく環境負荷の低減も見込めます。
こうした省人化や無駄の削減に加え、前述のとおり、短工期での建築により人件費を削減できることから、 serendix50の販売価格は550万円(税別、基礎、内装、その他付帯工事別)と、一般的なRC造の住宅に比べ、安価な設定となっています。
一方で、3Dプリンター住宅の課題としては、「長期的な耐久性」「出力物の品質均一化」「コスト削減と自動化」などが指摘されています。コスト削減については、現時点では現行の建築基準法の要件を満たすために鉄筋を入れて建築していますが、将来的には建築基準法の要件を満たしつつ無筋化を実現し、さらなる工期の短縮とコストの削減につながることが期待されます。
写真 serendix50

(資料)セレンディクス社提供
図表 建築工事の流れ

※詳細は経済月報4月号に掲載しております。ぜひ、ご覧ください。
(2025.4.11)