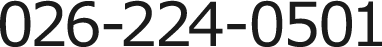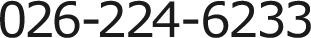「農業は楽しい」成功の鍵<2016.04.20>
県内における若者の新規就農者は、農業への関心の高まりや自治体の後押しもあり増加傾向にあります。各自治体ともに、人口増や産業振興の一環として農業への支援を厚くしています。長野県の調べによると、2009年度に178人だった40歳未満の新規就農者は、2013年度には245人になっています。
一方で、新規就農者の約3割は数年以内に離農しているという現実もあります。農業で食べていくというのは一筋縄ではいきません。就農後、事業を軌道に乗せている人はどのような点を克服してきたのか。佐久穂町で「のらくら農場」を営む萩原紀行さんを訪ねました。
萩原さんは千葉県の出身。埼玉県で有機農法を学んだ後、18年前に佐久穂町に移住し農業を始めました。最初は失敗の連続で、ようやく軌道に乗ったのは3年目あたりから。きっかけは「農業を科学的に分析し、経営の視点を取り入れたこと」です。
まず、良い作物を作るためのメカニズムを探っていきました。同じ農業の中でも有機農業は殊更に難しく、コストや手間がかかります。畑にはいつくばって作物と会話しながら、土壌の分析をしてデータを蓄積。そして、作業の効率化を推し進めながら、コストや手間に見合った値を付け、利益がでる経営体にしていきました。
70アールから始めた「のらくら農場」は、現在約4.5ヘクタールにまで広がり60種類以上の野菜を栽培しています。多品種栽培は煩雑な作業が目白押しです。4人のスタッフを通年雇用し、細かい作業を極力効率化しながら、栽培メカニズムの知識を共有してこなしています。
萩原さんは「面白そう、楽しそうという思いで走ってきただけ」と話されますが、農業を楽しいと感じることこそ最も重要な成功の鍵なのかもしれません。
業務をさらに拡大し、他の農家との連携で農産物を安定供給することが「のらくら農場」の次の目標です。「農作物を売る秘訣(ひ・けつ)は、顧客の望む期間に求める量を確実に供給すること」、「そのため、栽培メカニズムの知識を共有した農家が連携することが必要」と萩原さんは語ります。そして、「いつも買っていただいているご家族に喜んで欲しい。あの店長さんが自信を持って売っていける作物を作りたい」と取引を続けるお客様の声に精いっぱい応えていきたいと続けられました。農業を軌道に乗せるには「ファンづくり」ということも欠かせないでしょう。
環太平洋経済連携協定(TPP)は大筋合意を得ており、日本の農業が今後世界の荒波にさらされていく可能性は大です。その時に生き残るのは、科学と経営の考えを持ち、ファンと歩める農業なのだと思います。
(初出)朝日新聞平成28年4月20日朝刊「けいざい応援通信」『農業は楽しい、成功の鍵』
このページに関するお問い合わせ
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233