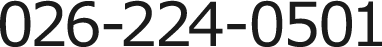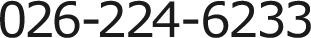注目集める信号機のない円形交差点の一種「ラウンドアバウト」
交差部で発生する事故のうち、約6割は信号のない交差点で発生しており、そのうち6割弱が出会い頭による事故です。また、信号交差点でも、信号無視や信号切り替わり時の無理な交差点進入による出会い頭事故が発生しています。一方、交差する方向に横断歩行者や車両がいないのに、赤信号により相当時間停止することもあることから、安全性を確保しつつ効率的な交差点制御方式の導入・普及が求められています。
こうした中、信号機のない円形交差点の一種である「ラウンドアバウト」への関心が高まっています。信号機のある交差点に比べ事故が少なく安全とされ、停電時も機能することから東日本大震災を機に注目度が上昇、一部自治体で導入の動きが進んでいます。認知度の低さなど課題はありますが、国も本格導入の検討に乗り出しており、普及への環境が整いつつあるといえます。
ロータリーと異なり環道走行車両が優先するラウンドアバウト
ラウンドアバウトとは、交差点の中央に円形地帯(中央島)が設けられており、自動車は中央島に沿った環状道路(環道)を時計回りの一方向に通行する円形平面交差点です。
走行する際に、一律のルールがないロータリーとは異なり、環道を走行する車に優先権があり、信号や一時停止の規制を受けずに走行できます。2013年6月の道交法改正でルールが明確になりました。交差点に進入する車両は手前で一時停止するが、環道に通行する車両がなければ徐行で左折して環道に入って時計周りに走り、そのまま行きたい目的の方向へと左折して抜けていくことができます。
英国では1960年代からラウンドアバウト導入のための調査、研究が行われ、70年代から普及しました。この実績に基づき、米国でも90年代後半からいくつかの州で設計ガイドラインが発行されてラウンドアバウトを導入、2000年代には連邦レベルで普及するなど、欧米の多くの国で導入されています。
長野県内では飯田市東和町交差点の既存信号機を撤去し交差点を改修する全国初の試みにより、2013年2月に導入され、現況の機能を残しつつ、安全性の高い交差点に改良されました。また、軽井沢町でも本格導入に向けて社会実験が行われており、今後、須坂市や安曇野市でも導入が予定されています。
車両速度低下による安全性向上や信号停止しないことによる燃費抑制などの効果を見込む
軽井沢町の六本辻交差点で2012年11月から実施したラウンドアバウト社会実験の一環のアンケート調査では、六本辻交差点の全体的な印象が、「良くなった」が51%、「悪くなった」26%、「変わらない」11%と回答しており、自由意見でも安全性が向上したなどの肯定的な意見が寄せられています。
その一方で、「自動車が一時停止をほとんどしないために、自転車の場合は今までより危険度が増した」や「ラウンドアバウトを造るには交差点が狭い」といった意見もみられます。
このため国土交通省では、日本の道路特性や交通状況などを踏まえてラウンドアバウトを整備する上で求められる技術的な課題を整理する検討会を2013年9月に設置し、検証を始めています。
ラウンドアバウトを導入することにより、交差点内での車両速度が低下し、右折など交錯箇所が減少することで重大事故が抑制され、安全性を高める効果が見込まれています。また、交通量が同程度であれば通過時間の短縮や信号停止のない燃費の抑制といった効果も期待されています。さらに信号が不要となり、維持管理コストの削減や災害による信号機倒壊の危険がなくなるなどの効果もあります。
交通量が多くなると徐行による渋滞が起きやすくなるなど、さばける交通量は1日15,000台程度である上、運転初心者や高齢者にとっては、環道へ進入するタイミングが難しい場合もあるようです。そのため、ルールの正しい理解のため導入ガイドラインの整備なども必要ですが、長野県など地方都市の安全で効率的な交差点方式としては合理的でもあり、今後他地域にも普及するか注目したいところです。
(2014.1.9)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
公共ソリューショングループ
電話番号:026-224-0504
FAX番号:026-224-6233