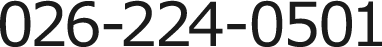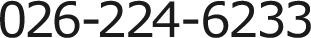道路整備が地域にもたらした効果
国や地方自治体の財政難を背景に公共事業費の削減が一段と進むなど、社会資本整備や社会資本整備の担い手である建設業界を取巻く環境は依然として厳しいといえます。
こうした現状の中でも、長年にわたり地域が要望し、地域活性化のために不可欠な社会資本は整備する必要があります。そこで、長野県内の道路整備の実例から、道路整備が地域にもたらした効果を考えます。
開通から5年が経過した伊那木曽両地域を結ぶ国道361号権兵衛トンネル
地域の評価が高い道路の一つに、着工から12年を経て主要部が開通した伊那木曽連絡道路があります。
伊那市と木曽町を結ぶ全長約20kmの地域高規格道路(国道361号)で、1994年に着工され、現在も建設が進められています。
国道361号の車両通行不能区間解消、伊那木曽両地域の交流促進、交通利便性向上の3つを目的とした道路であり、2006年2月4日の権兵衛峠道路および姥神峠道路の姥神トンネル以東区間の開通により、主要部が開通しました。このため、今年は開通5周年に当たります。
開通前、伊那路と木曽路の間には中央アルプスがそびえ、標高1521mの権兵衛峠を越えないと往来できませんでした。しかし、山を貫くトンネルを建設する難工事の末、冬の間通行できなかった閉鎖区間も解消され、全線が年間を通して走行可能となりました。これは、両地域にとって画期的な出来事です。
夏期、車で90分かかっていた伊那市-木曽町間の所要時間が約半分の50分に短縮され、交通量は約15倍。さらに、冬期は通行できなかったため、両地域の往来には北上し120分かけて塩尻市を経由するか、南下し190分かけて飯田市などを経由するしか方法がありませんでしたが、北上ルートは約70分、南下ルートは約140分短縮され通行不能区間も解消しました。しかし、効果はこれだけではありません。
買い物など生活圏の拡大、雇用機会増加、医療連携などが進み、伊那木曽地域が身近な存在に
開通後、新たな配送ルートの確保により、木曽地域にも大手コンビニエンスストアが7店出店、木曽から伊那の大規模商業施設の利用等買い物機会が増加し、両地域の生活圏が拡大しました。
また、厳しい雇用情勢が続き、新規求人件数が減少傾向にある中、伊那地域では、木曽地域を募集範囲に含めた求人がでるようになり、木曽地域の伊那地域への雇用機会が増加しました。
さらに、両地域が合同でイベント、スポーツ大会を開催し、交流が頻繁に図られるようになりました。
一方、医療機関の間でも、診療科目の相互補完が可能になり、医師派遣などの連携が開始、合同消防訓練の実施、事故・災害時の協力体制が構築されるなど、地域住民の安全・安心が高まりました。
利用者へのアンケートでも道路の満足度は93%と極めて高く、お互いの地域が身近な存在になりました。
道路がつなぐ伊那、木曽、飛騨の3地域の連携による今後の産業振興・活性化に期待!
伊那木曽連絡道路を含む国道361号は、岐阜県高山市から木曽を経由し伊那市高遠町を結ぶ延長約152kmの広域的な幹線道路であり、接続する国道と連絡することにより、伊那木曽地域と飛騨地域のみならず、関東、中部、北陸を結ぶ広域ネットワークとして重要な役割を担っています。
今後、国道361号の一層の整備促進が、広域観光振興とともに、地域連携による産業活性化につながる余地があります。特に、長寿、医薬品等の健康関連産業が3地域共通の特色であり、期待が持てます。3地域が連携し健康産業を重点的に育成支援する広域的産業振興ビジョンを推進することも良いでしょう。
道路開通による都市部とのアクセス向上を商機に生かし、事業拡大につながった地域企業もあります。
幹線道路網整備は、人・物・情報の流れを活発にするため、道路でつながる地域間のビジネス連携も促進されます。産業活性化による税収増の一部でさらに道路が整備されれば、地域も元気になります。
公共投資抑制は時代の流れともいえますが、この例のような道路整備は効果的で、地域における必要性も高いため、費用対効果を勘案しつつ、建設を推進することが望まれます。
(2011.6.21)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
公共ソリューショングループ
電話番号:026-224-0504
FAX番号:026-224-6233